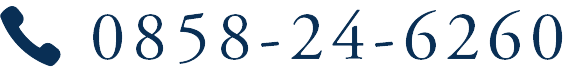お知らせ
映画『三島由紀夫VS東大全共闘 50年目の真実』から考える、日本の若者の無力感とその影響
2020.12.10
前回に引き続き三島由紀夫ネタです。
今年3月に公開された映画『三島由紀夫VS東大全共闘 50年目の真実』を観ました。三島由紀夫が自決する1年半前の1969年5月13日、東京大学駒場キャンパス900番教室で行われた、作家三島由紀夫と東大全共闘との伝説の討論会の様子、当時の関係者や現代の識者たちの証言から構成され、三島の人物像や生き様を検証していくドキュメンタリー映画です。
1960年代後半は大学の不正運営などに異を唱えた学生が団結し、学生運動は全国的な盛り上がりを見せていたようです。中でももっとも武闘派といわれていた東大全共闘。同じ年の1月には安田講堂を占拠し機動隊が出動、ガレキと火炎瓶で迎え撃つ学生が、機動隊の催涙弾と放水攻撃に敗北する事件を起こしていました。旧体制変革のためには暴力も辞さない東大全共闘は、「三島を論破し立ち往生させ、舞台の上で切腹させる」と盛り上がり、会場は異様なテンションが満ち溢れ、敵地には1,000人を超える学生が待ち構えます。中には三島側の楯の会や、全共闘と対立関係にある民青系全学連も潜んでいたそうです。三島は警視庁の警護の申し出を断り、単身で900番教室に入る時はまさに緊張感が最高潮。三島と東大全共闘の2時間半にわたる討論会。
三島は文豪でありながら身体を鍛え上げ民兵組織「楯の会」を作り、世界的に影響力のあるスーパースター、1,000人の敵をまとめて倒すつもりで討論会に来ているかのような雰囲気も伝わってきました。一方、迎え撃つ東大全共闘は三島を挑発したり、恫喝したり、内輪もめしたり、三島に挑みます。思想も立場も正反対。緊張感は伝わってくるもののおだやかな雰囲気。芥さんが子どもを抱いて討論したり、時に笑いがあったり、私が想像していたのとまったく違っていました。天才VS天才の饗宴が故に何を言っているのか分からないところがありました。言葉の銃で撃ち合い、論理の剣で斬り合う、スリリングな討論アクション。とっても濃い登場人物で、内容も濃すぎで、映画ポスターのキャッチコピー通り、三島の圧倒的な熱量を体感した、そんな映画でした。この時代の日本人、現代を再考し、発見が生まれる機会の得れる映画で、一人でも多くの方にご覧いただきたいです。
さて、思想的には相容れない三島と東大全共闘、後に三島自身が共通点があると語っていたようです。イデオロギーが異なる両者による「暴力」ではなく「言葉」で正面から渡り合う姿は見ていて、清々しいものがありました。三島はこの討論会で全共闘の説得を本気でかかっていたとも言われています。討論会の時点で三島は「いずれ楯の会が決起するときには、自衛隊も続く」という希望的観測を持ち、東大全共闘と論争するのではなく、共にクーデターに立ち上がる革命戦士をリクルートに行ったということです。確かに、全共闘は左翼過激派の運動であり立憲主義者ではなく、日本国憲法の下での立憲的な民主主義体制を守る気はない、その点は三島とは一致していたということです。敗戦後の日本を「対米従属」と断じ、戦後の民主主義を欺瞞と考え、実力行使をもって抵抗した全共闘。そこに三島はある種のシンパシーを感じていたのかもしれません。ただし、「天皇」をめぐる考え方は深い溝がありました。
この伝説の討論会の後、いずれも破滅への道となりました。三島は自衛隊に決起を呼びかけあえなく自決、学生運動は暴力的な内ゲバから「山岳ベース事件」、「あさま山荘事件」。
香港などの運動は、自分一人の言葉や行動が世の中を変えれるかもという一種の幻想や思い込みがあるからで、現代の日本の若者は、自分が何を言っても、何をしても、世の中はまったく変わらないという無力感に蝕まれているという思い込みがあるでしょう。地方選挙での投票率は20%を切り、8割の人は自分の一票では何も変わらないと思っているということです。それは現実ではなく、そういう気がするというだけです。皆が投票しないと、組織票を持っている人たちが永遠に勝ち続けます。自分の声は政治に反映されない、その積み重ねが無力感につながり、無力感は利己主義に繋がります。自分が何をしても世の中には何も影響が無いと思い込み、日常の生活、公益や公共の福祉に対しても配慮が無くなります。本来は、自分が一つでもささやかな“良きこと”を積んでいけば、社会は良くなるのです。まさに塵も積もれば山となる。間違いなく、皆が少しずつ石を積めば世の中は変わります。一人一人が自分ごととして関わっている社会で演じることが求められていると私は思います。現代の日本や日本人が精神的にも経済的にも依存、従順、洗脳され、本質的に独立していないことを三島は憂いていることでしょう。私の目には、今でも三島のギラリとした目が焼き付いています。
今年3月に公開された映画『三島由紀夫VS東大全共闘 50年目の真実』を観ました。三島由紀夫が自決する1年半前の1969年5月13日、東京大学駒場キャンパス900番教室で行われた、作家三島由紀夫と東大全共闘との伝説の討論会の様子、当時の関係者や現代の識者たちの証言から構成され、三島の人物像や生き様を検証していくドキュメンタリー映画です。
1960年代後半は大学の不正運営などに異を唱えた学生が団結し、学生運動は全国的な盛り上がりを見せていたようです。中でももっとも武闘派といわれていた東大全共闘。同じ年の1月には安田講堂を占拠し機動隊が出動、ガレキと火炎瓶で迎え撃つ学生が、機動隊の催涙弾と放水攻撃に敗北する事件を起こしていました。旧体制変革のためには暴力も辞さない東大全共闘は、「三島を論破し立ち往生させ、舞台の上で切腹させる」と盛り上がり、会場は異様なテンションが満ち溢れ、敵地には1,000人を超える学生が待ち構えます。中には三島側の楯の会や、全共闘と対立関係にある民青系全学連も潜んでいたそうです。三島は警視庁の警護の申し出を断り、単身で900番教室に入る時はまさに緊張感が最高潮。三島と東大全共闘の2時間半にわたる討論会。
三島は文豪でありながら身体を鍛え上げ民兵組織「楯の会」を作り、世界的に影響力のあるスーパースター、1,000人の敵をまとめて倒すつもりで討論会に来ているかのような雰囲気も伝わってきました。一方、迎え撃つ東大全共闘は三島を挑発したり、恫喝したり、内輪もめしたり、三島に挑みます。思想も立場も正反対。緊張感は伝わってくるもののおだやかな雰囲気。芥さんが子どもを抱いて討論したり、時に笑いがあったり、私が想像していたのとまったく違っていました。天才VS天才の饗宴が故に何を言っているのか分からないところがありました。言葉の銃で撃ち合い、論理の剣で斬り合う、スリリングな討論アクション。とっても濃い登場人物で、内容も濃すぎで、映画ポスターのキャッチコピー通り、三島の圧倒的な熱量を体感した、そんな映画でした。この時代の日本人、現代を再考し、発見が生まれる機会の得れる映画で、一人でも多くの方にご覧いただきたいです。
さて、思想的には相容れない三島と東大全共闘、後に三島自身が共通点があると語っていたようです。イデオロギーが異なる両者による「暴力」ではなく「言葉」で正面から渡り合う姿は見ていて、清々しいものがありました。三島はこの討論会で全共闘の説得を本気でかかっていたとも言われています。討論会の時点で三島は「いずれ楯の会が決起するときには、自衛隊も続く」という希望的観測を持ち、東大全共闘と論争するのではなく、共にクーデターに立ち上がる革命戦士をリクルートに行ったということです。確かに、全共闘は左翼過激派の運動であり立憲主義者ではなく、日本国憲法の下での立憲的な民主主義体制を守る気はない、その点は三島とは一致していたということです。敗戦後の日本を「対米従属」と断じ、戦後の民主主義を欺瞞と考え、実力行使をもって抵抗した全共闘。そこに三島はある種のシンパシーを感じていたのかもしれません。ただし、「天皇」をめぐる考え方は深い溝がありました。
この伝説の討論会の後、いずれも破滅への道となりました。三島は自衛隊に決起を呼びかけあえなく自決、学生運動は暴力的な内ゲバから「山岳ベース事件」、「あさま山荘事件」。
香港などの運動は、自分一人の言葉や行動が世の中を変えれるかもという一種の幻想や思い込みがあるからで、現代の日本の若者は、自分が何を言っても、何をしても、世の中はまったく変わらないという無力感に蝕まれているという思い込みがあるでしょう。地方選挙での投票率は20%を切り、8割の人は自分の一票では何も変わらないと思っているということです。それは現実ではなく、そういう気がするというだけです。皆が投票しないと、組織票を持っている人たちが永遠に勝ち続けます。自分の声は政治に反映されない、その積み重ねが無力感につながり、無力感は利己主義に繋がります。自分が何をしても世の中には何も影響が無いと思い込み、日常の生活、公益や公共の福祉に対しても配慮が無くなります。本来は、自分が一つでもささやかな“良きこと”を積んでいけば、社会は良くなるのです。まさに塵も積もれば山となる。間違いなく、皆が少しずつ石を積めば世の中は変わります。一人一人が自分ごととして関わっている社会で演じることが求められていると私は思います。現代の日本や日本人が精神的にも経済的にも依存、従順、洗脳され、本質的に独立していないことを三島は憂いていることでしょう。私の目には、今でも三島のギラリとした目が焼き付いています。